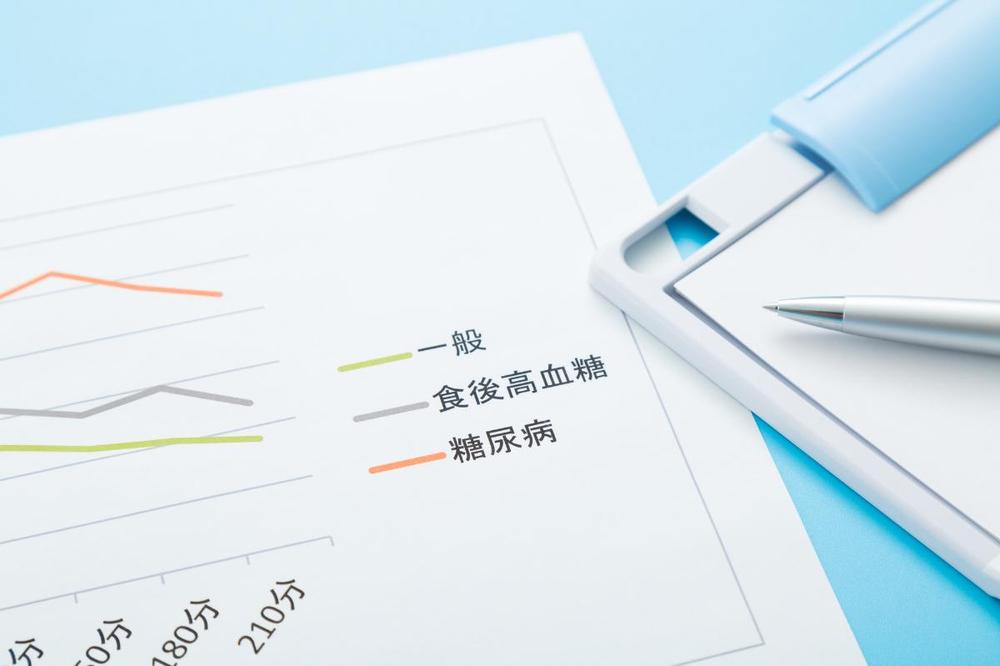2023年4月に、10年ごとに見直しが行われていた「母子健康手帳」の内容が変更されました。主な変更点は、産後うつなどの心のケアや地域の相談窓口の案内、父親・家族が記載する欄の追加、デジタル化の推進などです。また、近年は父親向けに「父子手帳」を発行する自治体も増えています。今回の母子健康手帳の主な変更点や、近年の子育て推進の動きについて解説していきます。
2023年4月より母子手帳が変わりました!変更内容や一緒に活用したい父子手帳も解説
- 健康情報

2023年4月に改定された母子健康手帳の主な変更点

2023年4月の母子健康手帳の改定では、主に産後のケアや、母親のみならず父親、家族、地域で子育てをすることを啓蒙しようとする姿勢がうかがえます。また、今後はデジタル化により対応していく意向が感じられます。
産後うつといった心のケアについて記載が充実するようになった
1つ目の変更点は、産後うつなど心のケアについての記入欄が充実するようになったことです。産後うつは、産後3か月以内に起こることが多く、気分の落ち込みや自責感などを生じるといわれています。場合によっては命を落とすこともあり、近年のコロナ禍で増加したという報告もあるため、産後の心のケアは大切な課題といえるでしょう。
具体的には、産後うつの可能性を得点化するEPDS(エジンバラ産後うつ病質問票)を行ったか問う欄が新設されたり、産後ケアを利用した日や方法について記入する欄が設けられたりするなどの変更がありました。
子育て世代包括支援センターへの相談を促す記載が追加
2つ目の変更点は、子育て世代包括支援センターへの相談を促すような記載が追加されたことです。家族だけでなく、地域で子育てを行うことを推進する姿勢がうかがえます。また、子育て世代包括支援センターなどのスタッフが記入する欄も設けられています。
父親・家族が記入する欄が追加
3つ目の変更点は、母親だけでなく、父親や家族が記入する欄が追加になったことです。これによって、母親だけではなく、父親などを含めた家族で育児を行うことを促しています。また、近年は家族の形態も多様化しているので、父親以外の家族が子育てに参加することも考えられます。名称は「母子健康手帳」ですが、ページ内では「保護者」という表現が使用されています。
デジタル化を推進
最後の変更点として、デジタル化の推進が挙げられます。近年はマイナンバーカードのデジタル化推進によって、健康保険証との一体化(マイナ保険証)も話題になっています。母子健康手帳のデジタル化も推進されており、マイナポータルで閲覧できる保健情報をより充実させるような取り組みが行われています。
▼関連記事はコチラ
【2024年完全移行?】マイナンバーカードが健康保険証に!PHR活用におけるメリットとは2023年4月の改定でも引き続き名称は「母子健康手帳」

お伝えしたように、今回の改定では父親の育児参加を想定した変更がなされています。「母子健康手帳」という名称についても議論が行われていました。父親の育児参加や多様化する家族形態を踏まえるべきという意見や、国民に浸透している母子手帳という名称を残すべきなどの意見がありましたが、最終的には、引き続き母子健康手帳という名称が使用されることに決定しました。
自治体判断で独自名称の併記可能
引き続き母子健康手帳という名称ではあるものの、自治体の判断で独自の名称を併記することは可能になりました。自治体の中には、すでに独自の名称を併記している例もあり、自治体それぞれの個性を出すことにもつながるともいわれています。
父子手帳を発行している自治体も増えている

最近は「父子手帳」を発行している自治体も増えています。名称はそれぞれの自治体で異なりますが、父親向けに、妊娠・出産から子育ての期間までお子さんとご家族の記録を残せるものになっています。また、父親が育児を行う上で役立つ情報も掲載されています。
それぞれ母子健康手帳を発行する窓口で、希望者に配布している例が多いようですが、自治体によってはオンラインでダウンロードできるものもあります。配布先についての詳細は、お住まいの自治体のHPをご確認ください。
まとめ|母親以外も子育ての参加を
今回の母子手帳の変更では、母親のみならず父親や地域で子育てを促すような取り組みが見受けられます。家族の形態が多様化する中、母親以外の子育ての参加が今後はますます重要になっていくでしょう。自治体によっては、父親向けに「父子手帳」を発行している例もあります。このような取り組みも活用して、家族で子育てをしていきましょう。
▼おすすめの書籍紹介
「ポストイクメンの男性育児 -妊娠初期から始まる育業のススメ」
改正介護・育児休業法により、男性育児の増加が期待される中、
男性の育児には様々な問題点が存在し、孤立する父親は少なくない。
父親たちが抱える悩みの原因から解決策、そして今後望まれる
社会体制について、産婦人科医および産業医として妊娠・出産・
育児の現場を見てきた男性筆者が綴る1冊。
著者 平野翔大
Daddy Support協会代表理事。
産業医・産婦人科医・医療ライター。

おすすめの資料